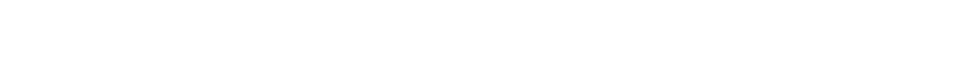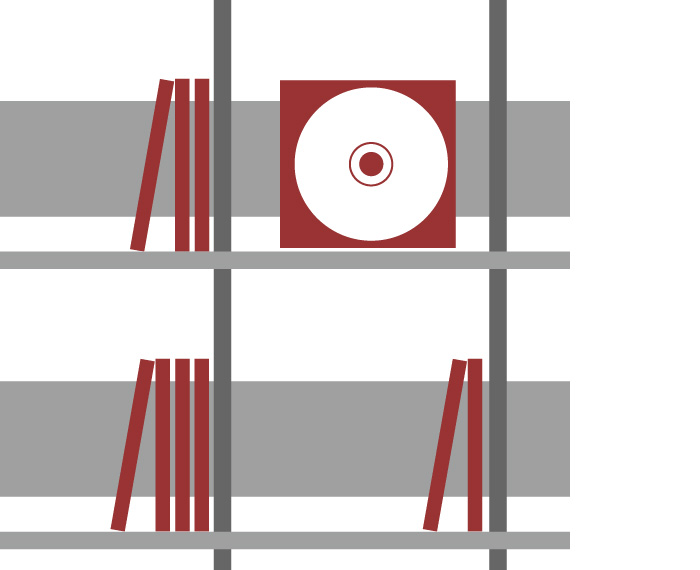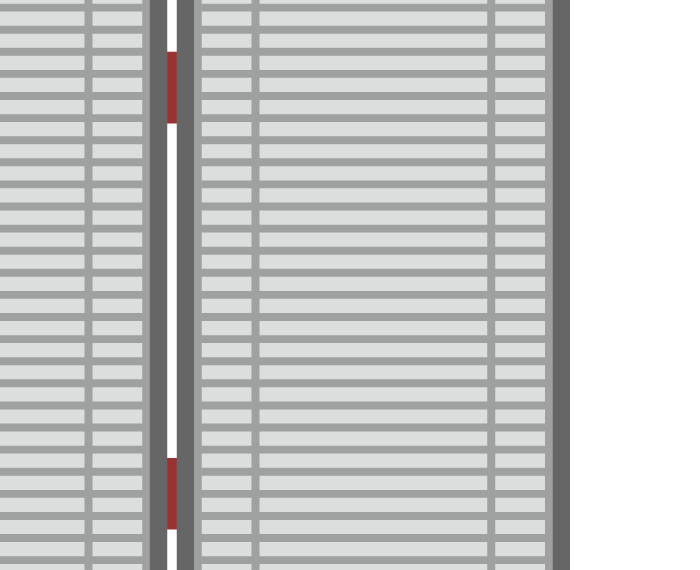福島県郡山市にあるインテリアショップ「Labotto Living Style(ラボットリビングスタイル)」は、幅広いインテリアスタイルや多様な生活シーンに対応する魅力的なアイテムを、独自の視点で厳選して取り揃えています。数多くのメーカーの家具やインテリア雑貨の中から、お客様のご要望やお好みに最適な提案を行っています。
今回、その施設内に移築された木造平屋の住宅をお借りし、「ladder 見せる収納ラック」シリーズおよび「Cavalletto 無垢材による収納ラック」シリーズの撮影を実施いたしました。この住宅は、釘や金物を使用しない伝統的な在来軸組工法で建てられており、日本らしい落ち着いた空間が広がっています。室内には囲炉裏を囲むように配置された正方形のダイニングテーブルと造り付けの長椅子が設けられ、建物全体と調和した内装となっています。また、そこから一段高く設えられた畳の間は玄関へとつながる広々とした空間であり、独自の和風モダンな解釈が施されています。

壁に立て掛ける本棚 BSL-01-H/L
この本棚は、すべての棚板とフレーム上部を壁に寄りかからせる構造で成立する、持ち運び可能な“立てかけ式”の収納家具です。設置には工具や固定具を必要とせず、壁に軽くもたれかけるだけで機能するシンプルな仕組みが特徴です。
本来は本棚として設計されていますが、その自由度の高さから、さまざまな用途に柔軟に対応します。たとえば玄関近くに置いて、お気に入りのスニーカーや小物をディスプレイするラックとして使用したり、寝室の一角に設置して、アクセサリーや帽子、ハンドバッグ、スカーフなど外出時の必需品をまとめて収納するなど、用途に応じてファジーに活用できます。
ハイタイプ Hとロータイプ Lがあります。

構造上、安定性に不安を感じる方もいるかもしれませんが、実際には荷物を載せることで荷重が下方向へと加わり、重心が自然に壁側へ移動するため、安定性はむしろ増します。床との接点を支点にしながら、荷重が増すことで壁との密着度が高まり、基準内の使用であれば転倒はまずありません。
このように、壁にもたれかけるだけというミニマルな設置方法でありながら、荷重によって安定性が増す合理的な設計は、家中どこでも簡単に収納スペースを確保したいというニーズに対して、非常に有効な選択肢となります。










脚立型コートハンガー CH-11/12/15
この木製コートハンガーは、設置場所を選ばないフリースタンディングタイプです。落ち着いたダークブラウンの色味が空間にすっきりとした印象を与え、和室・洋室問わず、どんなインテリアにも自然に馴染みます。バリエーションとして、用途や設置場所に応じて選べる1段・2段・5段タイプを展開しています。構造は、2枚の木製フレームを蝶番でつなぎ、イーゼルのように脚を広げて自立させる仕様です。このシンプルな構成により、道具を使わずすぐに設置できる手軽さがあり、使わないときは折りたたんで省スペースに収納できます。底面には滑り止めシートを前面に貼付しており、フローリングの上でも滑りにくく、安心して使用できます。玄関、寝室、リビングなど様々な場所で、アウターや帽子、バッグなどを一時的に掛けておくための補助的な収納として活躍します。



衣桁屏風型ハンガーラック CH-11L/12L/15L
「衣桁(いこう)」は、伝統的な日本の住宅で古くから使われてきた、衣服を掛けるための家具です。このプロダクトは、そんな衣桁の持つ機能性や美意識を現代の生活空間に取り入れられるよう、ミニマルなデザインで再構築した木製の衣桁型コートハンガーです。

もともと「衣桁」は着物を掛ける目的で鳥居のような形をしており、「衣文掛け(えもんかけ)」や「衣架(いか)」とも呼ばれていました。その中でも屏風のように折り畳み式で開閉可能なものを「衣桁屏風」と呼び、従来の衝立式と区別するようになりました。衝立式は室内装飾や「衣桁飾り」として嫁入り道具にも用いられることが多く、それに対して屏風型は部屋の隅に置き、羽織や外套を掛けておく、いわば現代のコートハンガーのような使われ方をしてきました。折り畳み可能なため使用しない時は簡単に収納でき、省スペースに貢献しました。


しかし、現代の一般家庭では衣桁屏風をほとんど見かけなくなりました。その理由としては、機能的には優れているものの、デザインが現代の室内空間に馴染みにくいことが挙げられます。また、本来の衣桁屏風は、和室特有の「長押(なげし)」と呼ばれる構造体の下端(約1800mm)と高さを揃えることで、空間に統一感をもたらします。しかし、長押が存在しない現代の和室やマンションの畳コーナーでは、上部空間が間延びした印象となり、衣桁屏風が綺麗に収まらないという問題があります。このような課題を解決するため、本プロダクトでは伝統的な衣桁屏風の特徴を踏まえつつ、装飾を削ぎ落とした軽量かつミニマルなフレームを採用しています。さらに脚立型コートハンガーと共通の構造を活用し、蝶番を長手側に設けることで、現代住宅の空間にも自然に馴染む、シンプルで美しい衣桁屏風の形を追求しました。





帆布ポケットラック POC-01/02
この布製ポケットラックは、A4サイズよりやや大きめの本や雑誌をゆったりと収納できる、丈夫な帆布素材のラックです。本や雑誌はもちろん、日用品や衣類、小物など少し大きめのアイテムもラフに収納できるため、リビングや子ども部屋、ワークスペースなど幅広いシーンで活躍します。設置は壁に立てかけるだけのシンプルなスタイルなので、省スペースに収まりやすく、限られた空間でも圧迫感なく使える点が特長です。バリエーションとして、収納量や用途に応じて選べる6段タイプと12段タイプを展開しています。
帆布ポケットはお客様ご自身で取り付けていただく仕様で、木製フレームに組み込まれたアルミパイプに、長い帆布を織り込むように通し、ボタンで固定するだけの簡単な構造です。取り外しも容易で、ポケットが汚れた場合は外して洗濯できるため、衛生的に長くお使いいただけます。


スリッパラック SR-06-H/L
このプロダクトは、スリッパを美しく見せながら収納するためにデザインされた、アルミ製のスリッパラックです。薄いアルミプレートを前後に交互に配置し、その間にスリッパを挟み込むように収納する構造により、スリッパの甲部分が自然と整い、展示するように並べられます。単なる収納としてではなく、スリッパそのものを空間に調和する「見せる道具」として捉えた、展示的な収納スタイルを提案しています。

「スリッパ」という言葉はカタカナ表記であることから、外来語と思われがちですが、実は日本独自の発明に由来しています。明治初期、開国により来日した西洋人の土足文化に対応するため、日本で生まれたのがスリッパの起源です。日本では室内で靴を脱ぐ習慣があったため、当初は「靴の上から履くオーバーシューズ」として考案されましたが、次第に日本人自身の生活に取り入れられ、現在のような室内履きとして定着しました。


構造的に見ると、スリッパは西洋の靴よりも、むしろ下駄や草履といった日本の伝統的な履物に近い、非常にシンプルで合理的なつくりをしています。その清潔感や最小限の構成は、日本的な美意識やミニマルな感覚とも深くつながっています。
このスリッパラックは、そうした日本文化に根ざした生活道具を「ただしまう」のではなく、「あえて見せる」ことで再構成した提案です。特に玄関という限られた空間において、スリッパの甲部分が整然と並ぶ様子は、実用品でありながらも美しさを感じさせ、まるで展示品のような佇まいを演出します。デザイン性の高いスリッパと組み合わせることで、その空間はさらに洗練された印象へと変わります。





この事例と関連するプロダクト
梯子のように立て掛けて使う収納ラック。モノを美しく見せながら収納、展示。
ダークブラウンのフレームで展開するコートハンガー、シェルフ、ミラー、屏風型パーティションも。
その他の事例を見る